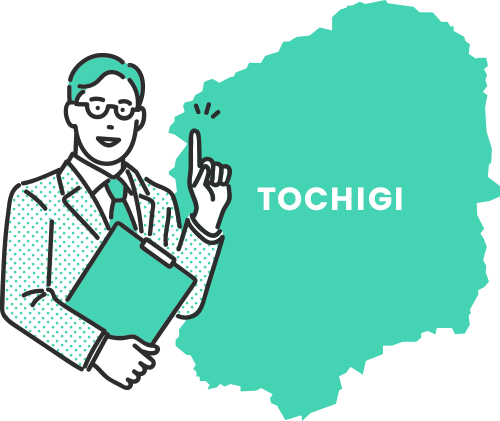おいしくて楽しい! この街の名物
染谷 典さん
新しい発想×昔ながらの製法で、いままでにないどら焼きを 暖簾をくぐると、雑誌の切り抜きが壁一面に飾られた店内に、どら焼きが種類ごとにトレーに収められ、ずらりと並んでいる。その光景は、まるでパン屋かカフェのよう。「バタどら」や「小豆と栗どら」をはじめとした定番から、「桜バター」や「よもぎきなこ」などの季節もの、さらに「マシュマロチョコ」や「モンブラン」といったニュータイプの商品まで、常に20~30種類のどら焼きがそろう。ポップに目をやると、「全身に塗りたい香りとコク!」(桜バター)や、「ポーチに入れたい程の好感!」(桜小豆)など、思わずクスっとしてしまうような、遊び心とパンチのきいた文字が躍っている。 「うちでは、どら焼きの皮のことを“バンズ”と呼んでいて、『バンズで挟めば、それはもうどら焼きだ』というルールを、勝手に決めているんです」 そう話す店主の染谷さんが、これまで手がけてきたどら焼きは120種類以上。コロッケやハンバーガー、お惣菜(!?)などの変わり種にも挑戦してきた。といっても、試作の方法はいたって真面目だ。染谷さんは、女性スタッフの意見も取り入れながら何度も試作を重ね、納得のいったものだけを店頭に並べている。また、県内はもちろん、東京の和菓子屋などへも、定期的に足を運ぶ。 「名店と言われるところは悔しいけどおいしくて、刺激を受けますね。何が違うんだろうって、店に帰ってきては材料を見直したり、作業工程を変えてみたり、けれど結局、うまくいかなくて元に戻したり……。そんなことばかり、ずっとやっています」 皮の生地には、「イワイノダイチ」という栃木県産の小麦粉や、大田原産の卵など、できるだけ地元のものを使用。防腐剤や保存料は使っていない。それを、熱伝導率の高い銅板で、一枚一枚、片面が焼けたら裏返してもう片面を焼くという、昔ながらの“銅板一文字の手焼き”を今も続けている。多いときには、一日500~600個分の皮を焼くこともあるという。 「最近は、機械を使って焼くフワフワな食感の皮が多いなかで、しっかりとした歯ごたえがあるのが、うちの特徴。これだけは変わらずに、守り続けています」 栃木へ戻るつもりは、まったくなかった 東京で生まれ育った染谷さんが、両親の地元である間々田へ引っ越したのは、中学3年生のこと。その後、高校3年間をこの地で過ごしたが、大学進学をきっかけに、また東京で一人暮らしを始めた。卒業後は、海運会社に3年半、アパレル会社に6年半勤め、アパレル時代には、海外での買い付けも経験した。「栃木へ戻るつもりは、まったくなかったですね」と振り返る。 そんな染谷さんが地元へ戻る決心をしたのは、三代目として和菓子屋を切り盛りしていた伯父さん(母親の姉の夫)が80歳になり、引退して店を閉めるのを決めたことがきっかけだった。 「母も、退職していた父も和菓子屋を手伝っていて、たまに電話で話すと、店を閉めることをとても残念そうに思っているのが伝わってきて。ちょうどそのころ、ぼくは独立して自分の店を開きたい、なかでも飲食関係がやりたいと考えていたこともあり、継ぐ決心をしたんです。また、当時はなんとなく地元に苦手意識があって、それを克服したいという気持ちも、少なからずありましたね」 老若男女、誰もが気楽に立ち寄れる店に Uターンしてからは、名物だった饅頭をはじめとした、和菓子づくりに没頭。失敗を繰り返しながら、約35種類の和菓子をつくり続けてきた。そのなかで、どら焼き専門店へと業態を変えたのは、どんな理由からだろう? 「当時、調査をしてみたら、お客さんの95%くらいが60歳以上の女性でした。僕は、その年齢層を下げて、若い人や男性も含め、老若男女が気楽に来られる店にしたかったんです」 そこで、和菓子屋を続けながら、まずは5年半前に茨城県の古河市に1号店を、その2年後には和菓子屋を辞めることを決意すると同時に、間々田に2号店を、さらに2年後に、小山駅のほどちかくに3号店をオープンした。 「数多くある和菓子のなかから、どら焼きに絞ることにも迷いはありませんでした。どら焼きは、子どもから年配の方まで誰もが好きで、和洋どちらの食材にも合い、表現の幅も広い。実は、定番商品の一つである『バタどら』は、和菓子屋だったころから人気商品の一つだったんです」 生産者や商店主のみんなと、一緒に盛り上がっていきたい 和菓子屋を継いだばかりのころは、ネーミングから使う素材まで、地元色を出そう、出そうとしていたという。けれど、それは表面的なものとなってしまっていたのか、最初は売り上げが伸びるが、リピートにはつながらなかった。そのため、あえて今は、地域らしさをそこまで意識はしていない。 「単純に、おいしいからまた食べたい! デザインが可愛いから、面白いから手土産に持っていこう! その繰り返しのなかで、『間々田といったらワダヤのどら焼きだよね』と名物になっていく。それが大事なんだと、失敗もしながら(笑)、気が付きました。どら焼きは、手を汚さずにワンハンドで食べられます。ファーストフード感覚で気軽に、おいしいどら焼きを楽しんでもらえたら、それが変わらない思いです」 現在でも、古河のカボチャやニンジンなど、地元の食材を使ったどら焼きをつくっているが、小山のハト麦など、少しずつ新たな特産品を使った商品にも挑戦していきたいと考えている。一方で、染谷さんは、音楽ライブやマルシェ、農家の収穫祭、雑貨屋の企画展など、仲間が主催するさまざまな地域のイベントにも出店。自身も「Mamamada FES」というロックフェスなどを運営している。 「地域の食材を積極的に使うのは、地元の農家さんと一緒に頑張っていきたいから、イベントに力を入れるのは、小山市はもちろん、県をまたいだ古河市や結城市で活動する魅力的な商店主たちと、みんなで一緒に盛り上がっていきたいから。それが結果的に、この地域全体を楽しくすることにつながっていったらいいなと考えています」