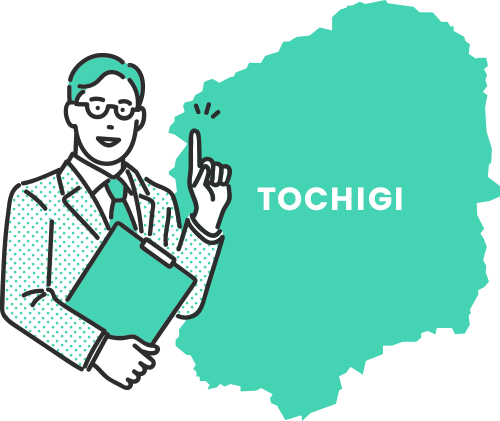小さな幸せが日常の中に
春山良子さん
農業研修や移住体験施設を活用して候補地探し 「どこかに移住しようか……」 そう切り出したのは充さん。2021年1月、東京に2回目の緊急事態宣言が出されたときのことだ。当時のことを、良子さんはこう振り返る。 「私たちは二人とも東京出身なのですが、私は小さいころから田舎暮らしに興味があって。夫もキャンプなどのアウトドアが趣味で、だんだん自然豊かなところで暮らしたいと考え始めたようです。これまでは東京を離れる理由がなかったのですが、コロナ禍でお店を思うように開けられないのを機に夫婦で話し合い、東京で居酒屋を経営しながら、もう一つの拠点を地方に持とうと動き出したのです」 最初に参加したのは、「農家のおしごとナビ」というサイトで見つけた、県北エリアで行われた国主催の農業研修。4泊5日の研修中に出会った農園のオーナーやスタッフのみなさんは裏表がなく、とてもやさしく接してくれた。県北エリアでは多くの移住者を受け入れているからか、オープンな人が多いところにも惹かれた。 「ただ、雪が降ったときの車の運転が、ちょっと心配でした。そんなとき、研修で知り合ったある年配の方が、『大田原市だったら、雪はそれほど降らないよ』と教えてくれて、移住先の候補に加えたんです」 次に利用したのは、東京・有楽町の「ふるさと回帰支援センター」内にある「とちぎ暮らし・しごと支援センター」だ。そこで、主に県北エリアを候補として考えていると伝えたところ、それぞれの担当窓口を紹介してくれた。なかでも、最初に連絡がついた大田原市に、まずは見学に訪れることに。 このとき滞在したのは、市の南部にある「ゆーゆーキャビン」というログハウスの移住体験施設。ここを拠点に移住コーディネーターに案内してもらいながら、農家や移住者のもとを訪ねて話を聞いたり、空き物件を見学したりして回った。そのなかで訪れた、裏にきれいな川が流れる小さな一軒家がとても素敵で、「こんなところに住んでみたい」と感じたという。その帰りに、近くの小学校に立ち寄ると、校長先生が「どうぞ見学していってください」と案内してくれた。 「児童数40人ぐらいの学校だったのですが、板張りの校舎は明るくきれいで、一人一台パソコンが支給されていました。校長先生は、『うちには不登校の子も発達障害の子もいますが、みんなで支え合いながらやっています』と話されていて、ここならうちの子たちもやっていけそうだと思ったんです」 さらに、2カ月のお試し移住を経て大田原に 4泊5日の滞在を終えて、東京に戻った良子さんは充さんと相談し、大田原市への移住を具体的に考え始めた。見学の際に気に入った小さな一軒家は築年数が古かったこともあり、近くで別の物件を探し、現在のこの一軒家(下写真)と巡り合った。 「ただ、賃貸ではなく売買物件だったので躊躇していたところ、大家さんが『試しに2カ月住んでみて、それで決めてくれたらいいよ』とおっしゃってくれて。2021年7月に私(良子さん)と子どもたち二人で、とりあえず引っ越してきたんです」 この2カ月間が、地域を知るために大いに役立った。 「近所のみんなさんはフレンドリーで、地域のことを教えてくれたり、虫取りが大好きな息子に捕ってきたクワガタをくれたり、本当に親切にしてくれました。そのうえ、家の周りの山々は緑が濃くとてもきれいで、夜には満天の星空が眺められるんです。夫は東京の居酒屋を経営しながらだったので、滞在は1週間ほどでしたが、もう早い段階で『ここに決めよう』と話していました(笑)」 近所の皆さんは地域のことや野菜づくりのことなど、親切に教えてくれる。 子どもたちが楽しそうだと、こっちも明るくなる! こうして新たな暮らしのスタートを切った春山さん家族。良子さんと子どもたち二人は大田原に移り住み、充さんは東京で居酒屋を経営しながら、月に10日間ほど大田原に滞在するという二拠点生活を続けている。 大田原に移り住んで一番うれしい変化は、子どもたちが学校に楽しく通うようになったことだ。 「二人とも、見学に訪れたときに校長先生とお会いした小学校に通っているのですが、学校に楽しく通えるようになりました。学校の行事にもちゃんと参加しているので、いろんな思い出ができて良かったなと思っています。何よりもすごく明るくなりましたね!子どもたちが楽しそうだと、こっちも明るくなります」 先生たちの顔が見えることもポイントで、安心して子どもを預けられるという。 「児童数が多すぎるというのもあると思いますが、東京にいた頃は担任の先生以外はほとんど顔も知らない方ばかりでした。それがこっちでは校長先生まで出てきてくれますからね。学校全体でちゃんと子どもを受け入れてくれていると感じます」 良子さん自身も、移住後すぐに家の前にある畑で野菜づくりを始め、最近は中古の耕運機も手に入れた。 「ジャガイモや玉ねぎ、ニンニク、スナップエンドウなど、いっぱい収穫できました。とれたての野菜は本当においしく、東京のスーパーに並んでいる野菜との違いに驚いています。子どもたちも、喜んで食べていますよ」 さらに、良子さんは近所にあるガソリンスタンドで、1日4時間ほどだがアルバイトもしている。 畑で野菜が多く収穫できたときは、自分で袋詰めをして、ガソリンスタンド内の商店で販売している。 「おばあちゃん、おじいちゃんをはじめ、地域の人が買い物に来てくれて、良く世間話をしています。バイトを始めたことで、地域について詳しくなりました」 一方、ご主人の充さんの楽しみは、庭に張ったテントで過ごすこと。ハンモックでくつろいだり、家族みんなでカレーを食べたり、「キャンプ場に行く必要がなくなった」と喜んでいるそうだ。 ハーブの栽培や道の駅での販売にもチャレンジしたい 春山さん家族は、大田原市西部の、周囲に山々が広がる地区に暮らしている。 「大田原市の中心部も見ましたが、街中では東京の暮らしと大きく変わらないのではないかと思い、あえて自然が豊かな地区を選びました。私たちはお店を始めるためでも、おしゃれな田舎ライフを楽しむためでもなく、家族で生活をするために移住先を探していました。それには自然が豊かで、地域の人もあたたかい今の場所が、ぴったりだと感じたんです」 他の移住者のように、「移住先でお店を開いた」、「新たな事業を始めた」というような“大きな変化”はないが、子どもたちが外を元気に走り回っていたり、充さんは庭でキャンプができてうれしそうだったり、毎日食べる野菜がおいしかったり、そんな“小さな幸せ”をたくさん感じるようになった。 それだけではない。東京ではどこへ出かけても人が多く、スーパーなどで騒ぐ子どもたちをつい怒ってしまうことや、些細なことでイライラすることがあったが、そんな小さなストレスも移住してからはなくなった。物理的な広さやゆとりがあると、気持ちにも余裕が生まれるのではないかと話す春山さん。 「子どもをやたらと怒らなくなった」 これも移住して良かったと感じることの一つだという。 「当面は、東京で居酒屋の経営を続けながら、徐々に大田原での生活も築いていきたい。これからは畑でハーブを育てたり、市内の道の駅で野菜を販売したりと、新たなことにもチャレンジしていきたいです」