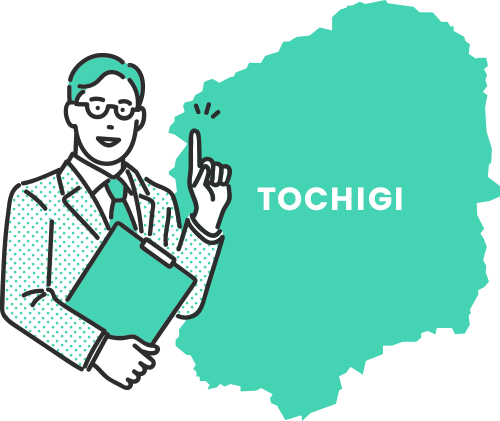ふらっと、深い出会いを
豊田彩乃さん
実家で過ごすように、ゆったりとくつろいでほしい 商店街に面した大きな窓が白み始めると、シャッターの開く音や、住民どうしが交わす挨拶の声などが聞こえてくる。ここは栃木県那須塩原市の黒磯駅前商店街。地域の人はもちろん、観光の人も行き交う、街の息づかいを身近に感じる場所に、2018年6月、「街音matinee(マチネ)」という名のゲストハウスが誕生した。 もし、街音に泊まったら、朝はいつもより少し早起きをして、7時からやっているという近所の和菓子屋さんやパン屋さんに出かけてみよう。近くには「1986 CAFE SHOZO」をはじめ人気のお店も点在している。少し足を伸ばして温泉につかったり、山登りを楽しんだり、自然に触れるのもいい。ただただ何もせず、街音の畳の上でゴロゴロと本を読む、という1日も贅沢かもしれない。 「まるで実家で過ごすように、ゆったりとくつろいでほしい」。それがオーナーの豊田さんの思いだ。 一方で、現在、豊田さんは那須塩原市の移住定住コーディネーターも務めており、「農業に挑戦したい」「お店を開きたい」などといった、移住を検討する希望者のニーズを聞きながら、一緒に街を巡ったり、人や物件を紹介したり、移住関係の補助金の申請などの手続きをサポートしたりといった仕事も手がけている。街音が、那須塩原を訪れ、この街について知るための〝起点〟になればという思いも持っている。 日本一周と世界各国の旅を経て知った、ローカルの魅力 豊田さんは埼玉県の草加市出身で、東京の大学に通っていた4年生のころ、留学のために1年間休学。資金を貯めようとアルバイトをすることにしたが、幸運にも、がん患者がタスキをつなぎながら日本を一周するというチャリティーイベントの運営スタッフに選ばれ、約半年かけて47都道府県を巡るという貴重な経験をした。 「このとき、日本には美味しいものや美しいもの、やさしい人など、知られていない魅力が山ほどあることを肌で実感しました。海外に留学する際も、いろんな地域を見てみたいと思い、アジアから中東、ヨーロッパ、アメリカまで、各国を巡ることにしたんです」 そんな旅の途中、イスラエルのパレスチナ自治区で滞在したのが、「イブラヒムピースハウス(通称:イブラヒム爺さんの家)」という名の宿だ。 「ゲストハウスの周囲の道路は舗装もされておらず、ちょっと危なっかしい雰囲気なのですが、そこにイブラヒムお爺さんの家があって、お爺さんがいることで、ツーリストたちがいっぱい来るし、地域の人や子どもたちも安心してそこを訪れる。そんな交流の起点となる場所って、素晴らしいなと感じたんです」 こうした世界各地や日本中を巡った経験から、地域に入り込んで、人と人の距離が近い関係の中で、いろいろなことを学びたいと考えるようになった豊田さん。そこで興味を持ったのが、地域おこし協力隊だ。「協力隊であれば、卒論を書きながらもすぐに地域に入っていろんな経験を積むことができるのでは」と考え、新潟や山形など、各地の自治体の情報を集めるなかで、選んだのが那須塩原市だった。 「那須塩原は、生活の場であると同時に、観光地でもあって、いろんな人の暮らしが交わる面白い場所だと感じました。また、現在、駅前で建設が進められている『まちなか交流センター』や『駅前図書館』の計画なども、当時から住民の皆さんが積極的にかかわって進められており、ますます地域が面白くなりそうだと実感したんです」 人と人が出会う、起点となる場所をつくりたい こうして那須塩原市の地域おこし協力隊の第一号として採用された豊田さんは、商工観光課の配属となり、3年間、国内外から観光客を呼び込むための様々な活動に取り組んだ。なかでも、企画を担当した観光ツアーのアイデアは、トラベルブロガーが日本の知られざる地域の魅力を探り紹介していくという「We Love Japan Tour2015」のHidden Beauty大賞で、準優勝にも輝いた。 また、黒磯駅前で年2回開催されているキャンドルナイトをはじめ、地域の活動にも積極的に参加。自分自身でも、地元農家とコラボしたさつまいもの収穫体験イベントや、ワイン用ぶどうの収穫体験、篠竹のかごづくり体験など、さまざまなイベントを企画している。 「今では、街じゅうに知り合いが増えました。多くの人と積極的にかかわるなかで、新しい発見があることを、身をもって体感し、そんな人と人が出会う、きっかけとなる場所をつくりたいという思いがますます強くなりました」 その場所が、まさに「街音 matinee」だ。黒磯駅前商店街でキャンドルナイトを主催する、黒磯駅前活性化委員会会長の瀧澤さん(上写真。一緒にバンドを組んで、キャンドルナイトで演奏している)の紹介で、もと紳士服店だったこの物件と出会ったのが2016年。 以来、豊田さんは準備段階からいろいろな人に関わってほしいと、2017年10月には栃木県による「はじまりのローカルコンパスツアー」を受け入れ、建物が持つ味わい深い良さはなるべく生かしながら、東京などの都市部から訪れた参加者と一緒に、壁塗りなどの改装を行った(下写真の布団ボックスも、いろいろな人に手伝ってもらいながらDIYで製作したものだ)。そのツアーをきっかけに、参加者と豊田さんは意気投合。同年代の建築士志望のメンバーや、篠工芸作家などと、夢を持つものどうしがお互いに応援しあう「あやとり」というグループも結成している。 「街音に泊まって、那須塩原の街をゆっくり巡ってもらえたらもちろん嬉しいですが、そうでなくても、いろんなイベントにちょっと顔を出していただくだけでもいい。そうやってさまざまな人が関わり、つながっていくなかで、この場所、この街がだんだんと色々な人にとっての〝大切な第二の拠点〟に育っていったら嬉しいですね」 そう話す豊田さん自身も、この街音を通じてたくさんの人と巡り合い、つながることで、どんどん那須塩原の街が好きになっている。