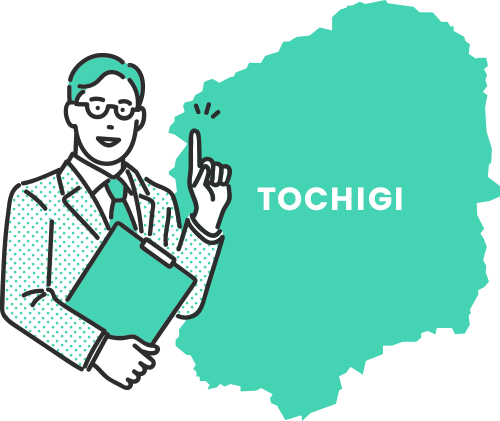家づくりを通じて、豊かな「地縁」を紡ぎたい
髙山 毅さん
代々商売をしてきた壬生の地で、暮らしと営みを 左は米穀店だったころの法被、右は「壬生町史」。 「これを見てください」と髙山さんが開いてくれたのは、明治の頃、壬生の町内にあった商店の名が記録された「壬生町史」だ。そこには、鍛冶屋、薪炭商、桶屋、左官などがずらりと並ぶ中で、「銅鐡打物商」として髙山さんの曽祖父の名と屋号紋が記されている。当時の屋号紋は、「澤デザイン室」の上澤裕一さんによってリデザインされ、山十設計社のロゴ(下写真)として、今も受け継がれている。 現在、髙山さんのアトリエと住まいがあるこの場所は、壬生城址にほど近い中心市街地にあたり、髙山家では代々この地で商売を手がけてきた。 「曽祖父が金物商、祖父がお米屋、父が紙器と、生業はそれぞれ違うのですが、代々ここに暮らし、商売を営んできました。だから、私もこの地を受け継ぎ、ここで生活しながら仕事をするというのが、自然なこととして頭にあったんです」 髙山さんは一人っ子で、両親が年齢を重ねてから誕生した子どもだったため、親の介護をする時期もおのずと早いだろうと自覚していたことも、Uターンを選んだ理由の一つだった。 顔が見える関係を大切に、地域ならではのつながりを 山十設計社のホームページを開くと、次のようなメッセージが記されている。 「衣・食・住の縮図である“家”づくりを通じて、モノと人が循環する地域ならではの『地縁』を紡いでいきたい――」 こうした髙山さんの思いのルーツも、生まれ育った壬生町にある。 「例えば、昔は、先ほど見てもらった鍛冶屋や桶屋などの商店が並んでいて、近所のお店で買い物をしたり、馴染みの職人さんに仕事を頼んだりというのが、日常だったと思うんです。私は今でも、おいしいものを食べたいときは行きつけのお店で店主とおしゃべりしながら味わったり、車のメンテナンスは同じ整備士さんにずっとお願いしていたり、顔が見える関係を大切にしています。そんな地域の豊かな人のつながりを、家づくりを通じて再び育んでいけたらと考えているんです」 近くにあるイタリアン・レストランの「Fill kitchen」(フィルキッチン)にて。 その挑戦の一つが、この土地の風土や気候に適した、つくり手の顔が見える道具や素材を発信する「てびき」という取り組みだ。 髙山さんは、家は建物だけでは完成しないと考えている。丁寧な暮らしを楽しんでいきたいと思ったとき、家という器だけでなく、そこで使う道具や、ふだん食べるものなど、衣・食・住すべての要素が大切になってくる。 「かぬちあ」の中澤恒夫さんによるタオルハンガー。 だからこそ、様々なつくり手と山十設計社のプロダクト「てびき」では、那須塩原市の金工作家「かぬちあ」の中澤恒夫さんが手がける靴べらやタオルハンガー、フックをはじめ、益子町に2015年に創業した手仕事集団「星居社」がつくる今の暮らしに馴染む神棚などを、自社のホームページで発信。それだけでなく、佐野市で90年以上続く「日本プラスター」の漆喰などの素材も紹介している。 「ただ、これらはオンラインでは販売していなくて。家づくりなどを通じて、顔が見える関係になった方だけに提供しています。それは、やはり山十設計社で建てる家をきっかけに、豊かな『地縁』を広げていただきたいと考えているからです」 刺激を与え合う、異業種のつながりから生まれた「octopa」 「octopa」の4人。左から上澤さん、髙橋さん、髙山さん、荒井さん。 もう一つ、目指すベクトルが同じ異業種の人たちとのつながりを大切に始まった取り組みが、「octopa」(オクトパ)だ。宇都宮市で「古道具あらい」を営む荒井正則さんと、芳賀町で「mikumari」という名のカフェを開く髙橋尚邦さん、那須烏山市を拠点に活動するグラフィックデザイナー「澤デザイン室」の上澤裕一さん、そして髙山さんの4人がメンバー。古き良きものを、衣・食・住をテーマに今の暮らしに馴染むものとして再現し、“フルダクト”として提案している。 「例えば、アームライトやミシン椅子など、デザイン性に優れたアンティークをリプロダクトしたものだったり、昔ながらの保存食にヒントを得たソースや調味料の瓶詰めだったり、4人それぞれの得意分野を生かして、現代に合うものとしてつくり出しています」 また、octopaとして、これまでに日本最大級のアンティーク・マーケット「東京蚤の市」に出店するほか、黒磯の「1988 CAFE SHOZO」や益子町の「スターネット」などのカフェでも、食とクラフト、アンティークをテーマにしたイベントを開催してきた。現在では、古道具あらいに併設された建物で、「オクトパ食堂」をオープンし、瓶詰めのソースや調味料を生かした料理を提供している。 地域に根ざす喜びを実感する日々 一方、暮らしの面では、髙山さんは奥さんと二人のお子さん、そして父親の5人で、アトリエに併設された住まいで暮らしている。奥さんも建築士として勤めているため、髙山さんも掃除や洗濯などの家事を分担したり、子どもたちの宿題や、父親の様子を見たりと、1日のなかにこうした仕事以外のやるべきことも組み込みながら行っている。 「今年92歳の父は、だんだんと介護が必要になっていますが、やはり一緒に暮らしている安心感は大きいですね。ふだんの様子がわかるからこそ、どんな介護サービスが必要か、どこの業者に頼もうかなどを、しっかりと検討できます」 2016年に、実家の土地にアトリエと住まいを建築したとき、髙山さんはバリアフリーはもちろん、1階にある父親の部屋の近くにトイレや洗面、浴室などの水回りも配置した。これにより、自宅で父親を介助するときの負担を軽くすることができた。 「実は、この家に暮らし始めて6年ほどの間に、父が倒れて救急車を呼んだことが何度かありました。そのときも一緒に暮らしていたからこそ、倒れたことに気づくことができ、すぐに搬送することができました。その後の通院をサポートできたのも、同居しているからだと感じています」 また、髙山さんは、父親から受け継いだ寺の役員や自治会の班長のほか、子ども会の育成会長など、地域の活動にも積極的に参加している。 「父は直接口には出しませんが、そろそろ私に町内の仕事を任せても大丈夫だと思ってくれたのかなと。というのも、デイサービスのヘルパーさんには、『うちの息子は一級建築士の仕事も、地域のことも頑張っている』と話しているそうなんです。きっと、この家のことも喜んでくれているんじゃないかな」 地域のお祭りなどにも携わる髙山さんは、「子どもの頃、楽しかった夏祭りに、今度は親として子どもたちと参加するなど、地域に根ざすのもいいものだなあと実感しています」と微笑む。 空き家を再生し、現代版の地縁でつながった街をつくりたい 最後に、そんな生まれ育った壬生町で、髙山さんが今後手がけていきたいことについて話を伺った。 「実は、このアトリエの2階はオープンスペースになっていて、ここでいろんな人が得意なことを教え合う、“寺子屋”のようなワークショップを開催できたらと考えているんです」 「ひび学舎」と名付けたこの取り組みのコンセプトは、次のとおりだ。 「使い、壊れ、捨てる」は「使い続け、傷んだら、繕う」に。「買っていたもの」は「育て、つくるもの」に。「古びたもの」は「活かし生きるもの」に。子どもから大人、つくり手も、暮らしに近い事柄を一緒に体験し、暮らしに持ち帰る。そんなきっかけを生み出す場に。 「例えば、『古道具あらい』の荒井さんがアンティークの磨き方をレクチャーしてくれたり、設計を担当させてもらった栃木市の『珈琲音 atelier』のオーナーにコーヒーの淹れ方を教えてもらったり、そんな様々なワークショップが開催できる場所になればと思っています」 レクチャーを行う人は壬生町に限らず、いろいろな地域から招きたいという。 「壬生町は、宇都宮市や栃木市、鹿沼市、下野市などの大きな街に隣接し、どこへでも行きやすく、どこからも来やすい。そんな特性を生かして、例えば、栃木市のコーヒーショップと宇都宮からワークショップに参加した人をつなぐなど、ここを地域と地域、人と人をつなぐ“ハブ的”な場所にしていきたいんです」 様々な地域の人が集うようになれば、いずれ壬生に住んでみたい、壬生でお店を開いてみたいという人も現れるのではないか。現在、壬生の中心市街地では、多くの商店街と同じように、空き家や空き店舗が増えつつある。一朝一夕にはいかないが、そんな空き家を一つひとつ人が暮らし生業を営む場所に変え、明治期の商店一覧で見たような多彩な生業の人が暮らし仕事を頼み合う、現代版の「地縁」でつながった街にしていきたい。それが髙山さんの大きな夢だ。 「街並みとして線にならなくてもいい。点と点が徐々につながっていくような、そんな空き家を生かした新たな試みに、私も自分の生業である建築の分野で携わることができたら最高ですね!」